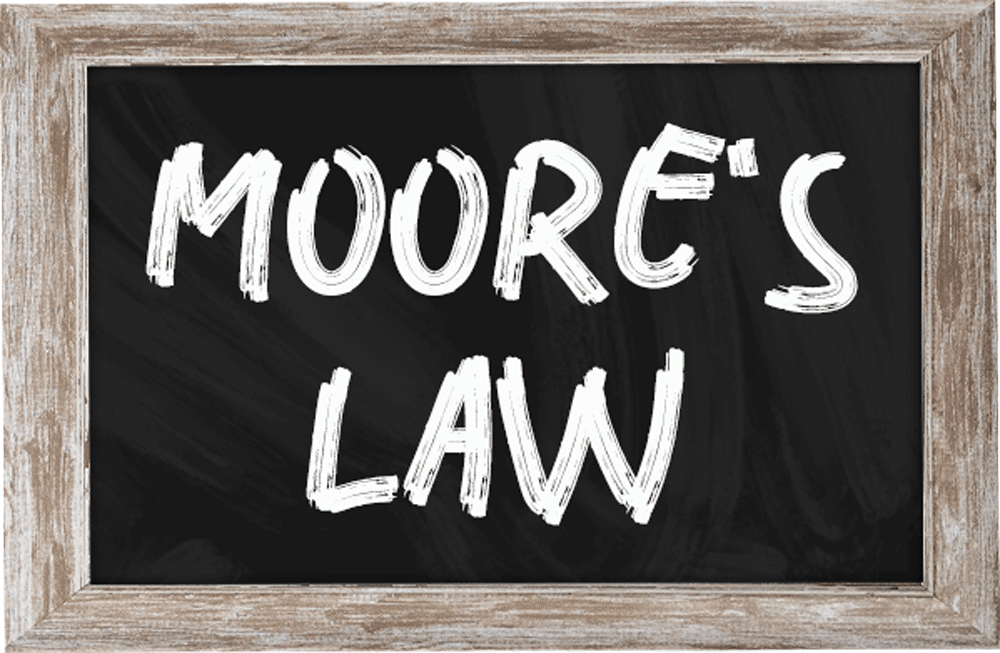174
ムーアの法則は、1965年にゴードン・ムーアによって提唱されました。この法則が具体的にどのようなものであり、どのような特徴を説明しているかを、この記事でご説明します。
ムーアの法則の意味
この法則は、1960年代頃にインテル社の創設者ゴードン・ムーアによって提唱されました。ムーアの法則は、コンピューターの性能の定期的な制御に関するものです。1997年にこの法則は研究によって確認されましたが、厳密に言えば、これは法則というわけではありません。
- ムーアの法則は、コンピュータや技術機器の性能がおよそ18か月ごとに2倍になるという規則を定めています。したがって、これは厳密な法則というよりも、経験則のようなものです。
- 当初、1年ごとに2倍になることが予測されていました。しかし、さらなる検証の結果、これは 2 年間に延長されました。
- ゴードン・ムーアは 1965 年、技術的および経済的要因が、技術的な端末機器や集積回路の開発において相互に作用するという彼の理論に基づいてこの法則を立てました。この期間、コストは変化しません。したがって、価格の上昇なしに、より高性能な機器が開発されることになります。
- 多くのチップメーカーは、インテル創設者のこの法則に従った結果、この法則が現実のものとなりました。製品はムーアの法則に従って製造され、その予測は現実のものとなったのです。
ムーアの法則の誕生の経緯
ゴードン・ムーアは、インテル社の共同創設者であり、半導体産業のパイオニアでした。1960年代、彼は、現代マイクロチップの発祥の地の一つであるフェアチャイルド・セミコンダクター社に勤務していました。
- 1965年、ムーアは雑誌「エレクトロニクス・マガジン」に、集積回路上のトランジスタの数は、生産コストが一定の場合、ほぼ毎年2倍になっているという観察結果をまとめた短い論文を発表しました。
- この観察は、当初は経験的な発見であり、物理法則ではありませんでした。その後、「ムーアの法則」として知られるようになり、コンピュータ業界全体のイノベーションと計画の指針となりました。その後数十年にわたり、ムーアは、18~24 ヶ月ごとに 2 倍になるという予測を修正しました。
技術的影響 – 小型化と性能向上
ムーアの法則は、何十年にもわたってマイクロエレクトロニクスの発展に影響を与えてきました。新しいチップ世代が登場するたびに、より小さなスペースにより多くのトランジスタを収容できるようになりました。
- 構造サイズは、1970 年代の数マイクロメートルから、現在では数ナノメートルにまで縮小しました。この小型化により、演算能力だけでなくエネルギー効率も向上しました。
- 同時に、トランジスタあたりのコストも劇的に低下しました。これらの進歩により、PC、スマートフォン、クラウドコンピューティング、人工知能の爆発的な発展が可能になりました。
ムーアの法則の限界
2010年代以降、ムーアの法則は物理的および経済的な限界にますます直面しています。
- 今日のトランジスタはわずか数ナノメートルの大きさしかなく、量子効果や熱効果がますます重要になっているため、これより小さな構造を安定して製造することはほとんど不可能です。
- さらに、新しい製造プロセスの開発コストは急速に上昇しています。また、発熱を制限しなければならないため、最新のプロセッサのクロック速度もほとんど向上していません。そのため、メーカーは、パフォーマンスの向上を図るために、並列処理や特殊チップにますます力を入れています。
代替案とさらなる開発
従来の小型化の限界を超えるため、研究者や産業界は、いわゆる モア・ザン・ムーアアプローチと呼ばれるものです。その中には、以下のようなものがあります。
- 3Dチップ設計:複数のトランジスタ層を積み重ねたもの
- 人間の脳を模倣したニューロモーフィックチップ、
- ビットではなく量子ビット(キュービット)を使用して、まったく新しい計算モデルを可能にする量子コンピュータ、
現代産業への影響
従来のムーアの法則の終焉は、次のような大きな影響をもたらしています。
- 人工知能(AI)分野では、ハードウェアの高速化よりも、アルゴリズムの改良によって進歩を図る必要性がますます高まっています。
- クラウド業界では、エネルギー需要が大幅に増加しているため、効率性と冷却が重要な課題となっています。
- 民生用電子機器分野では、イノベーションサイクルが鈍化しており、製品の寿命延長や新しいビジネスモデルの出現につながっています。